- Home
- 中国史史料研究会 会報第13号:試し読み
学会情報
7.22021
中国史史料研究会 会報第13号:試し読み
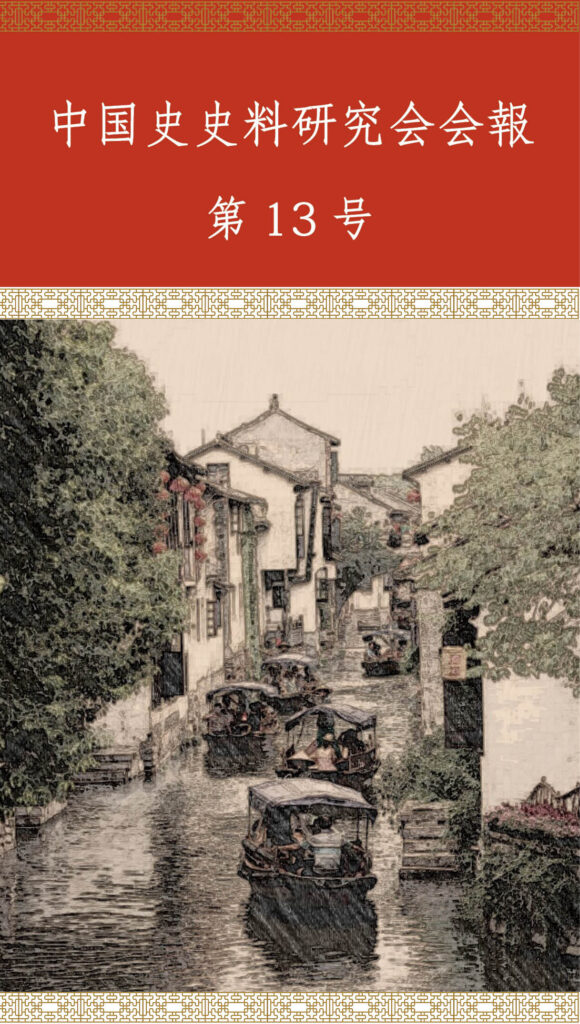
表紙は蘇州の市内を流れる運河の風景。
亀田俊和「亀田俊和の台湾通信 第14回」
今回は、台湾の政治について感じたことをつらつら書いてみたい。
ツイッターでもときどきつぶやいているし、別に隠すことでもないので書くが、私はかつて二大政党にあこがれていた。栃錦と若乃花あるいは大鵬と柏戸の二大横綱のように、交互に政権を担当して活発な政治が行われることを夢見ていた。しかし日本では、現在に至るまでその体制は実現していない。1度それらしき政権交代は起こったが、周知のとおりの状況で、わずか3年ほどで自民党一強の状況に戻り、野党はバラバラに分裂している。政党政治の観点では、私は現在の日本の政治に失望している。
そんな私から見て、台湾はまさに二大政党制が確立し、数年に1度健全な政権交代が行われている理想の地域であった。そのようなところに移住して、台湾の政治を直に見ることができる。これもまた、台湾に来る前に密かに楽しみにしていたことであった。
ところが実際に台湾に来てみると、事前に本で読んだり話で聞いていたりしていたこととは、何だか少し違うような気がしてきた。……
野澤 亮「青木 朋『三国志ジョーカー』(ボニータコミックス)」
さて本作品は『ミステリーボニータ』2010年の12月号から2012年9月号まで連載された漫画であり、三国時代を舞台にしたSF時代劇である。単行本全5巻が秋田書店から刊行されている。本作のあらすじは若き司馬懿が何故か洋装のスーツを身にまとい、近代文明の利器を用いて自身が仕える曹操・曹丕の周辺で起こる怪事件を解決していくところからストーリーは始まる。実は、司馬懿は2年前に未来の科学技術を操る怪人・諸葛亮に誘拐されていたのだ。なぜ自分がそんな目に遭うのか明らかになるまでは、スーツを脱がないと誓った司馬懿は怪人・諸葛亮を追うが、諸葛亮もまた司馬懿にご執心で、陰に陽にストーキングしていく。そこに曹操軍と劉備・孫権との戦いが絡むというものである。しかも前半ではおそらく誰しも諸葛亮自身が未来人だと思うだろう。ところがそうではなく、古代人の諸葛亮の身体を未来人が借りていたのである。
さてここからは本作の魅力をリアルタイム(といってもややタイムラグがあるが)な鑑賞体験の思い出話を交えて述べてみたい。……
佐藤信弥「竹内真彦『最強の男―三国志を知るために』」
日本に三国志マニアは数多存在するが、その多くが正史『三国志』(以下、正史と呼称する)などの史書によって後漢末~三国時代の史実や制度などを突き詰めるという方向に進み、文学としての『三国志演義』(以下、演義と呼称する)を正当に評価し、突き詰めるという方向にはあまり進まない。本書の序(7頁)に言うように、多くの読者は演義をベースとしたコンテンツから三国志を知ったはずなのに、熟知されないままに演義は打ち棄てられてしまうのである。同じく序(7頁)に「大して読まれもせぬまま、存在だけは知られている」という演義を読み込む面白さについて、三国志物語において「最強の男」とされる呂布の分析を通じて論じたのが本書となる。著者竹内真彦の専攻は中国文学、『三国志演義』に関する文献研究とのことである。本書は著者のこれまでの論文等をベースとした一般書である。
本書の構成は、本編が5章から成り、附章がふたつ、そしてコラムが計11編となる。コラムの題目を挙げておくと、それぞれ1「姓名字」、2「暦」、3「後漢の行政区分」、4「干支」、5「五行説」、6「八健将」、7「諡号と廟号」、8「『資治通鑑』と『資治通鑑綱目』」、9「『三国志平話』」、10「雑劇」、11「『花関索伝』」となる。……
山田崇仁「東洋学の名著 第三回:小倉芳彦『古代中国を読む』」
著者について
本書の著者である小倉芳彦は、1927(昭和2)年の生まれである(この年の3月、中国国民党総理孫文が、6月には中国古代史の泰斗王国維がそれぞれ世を去っている)。
小倉氏は、その後の第二次世界大戦までの間に幼少~青年期を経て、戦後歴史学会が戦前の皇国史観への反省からアカデミズムの傾向が大きく変化した時代に、その学問的基盤を構築している。その後、東京大学東洋文化研究所助手を経て、1953年より学習院に勤務し、教授を経て学習院短大学長、更には学習院学長という重職を勤められた。
本書について
本書は、今から約半世紀前の1970年代に、小倉氏が東洋史を志した経緯や、春秋時代を研究する上で重要な資料となる、『論語』・『春秋左氏伝』(以下『左伝』と略)・『史記』とどのように向き合ったかを述べたものである。そのため、研究書やそれをかみ砕いた一般書と言うよりも、むしろエッセイに近い著作である。
後に本書は、『小倉芳彦著作選』(全3巻)の第1巻に収録されたが、第1巻の後書きに本書刊行後「岩波書店らしくない」との批評が小倉氏の耳にも聞こえてきた旨の記述があるように、その異色のスタイルが多少の物議を醸したようである。
確かに、他の岩波新書とはずいぶんと毛色が異なるが、それ故に同時代的な空気感を残しつつ、研究者としての本質を述べる文体と内容とが、本書の特徴といえるだろうか。1970年代初頭と言えば、日本では学生運動が残り火となりつつあった一方、対岸では文革の一環としての非林非孔運動が吹き荒れるような状況であった。そのため、中国古典と向き合うという行為は、令和の時代とはまた違う気構えが必要だったのかもしれない。
では、ここから本書の内容をいくつか取り上げていこう。……






